『感情類語辞典』(アンジェラ・アッカーマン、ベッカ・パグリッシ著)は、小説における感情描写を練習するためのお役立ち書籍である。
ただし、見出し語(感情)がたったの75しか掲載されておらず、辞書としての役割を期待すると肩透かしを食らう。一般的な類語辞書とは似て非なるものであるため注意されたし。
筆者が本文中で述べているように、本書は『ブレインストーミングのための道具としてとらえてほしい』(引用 p.27)
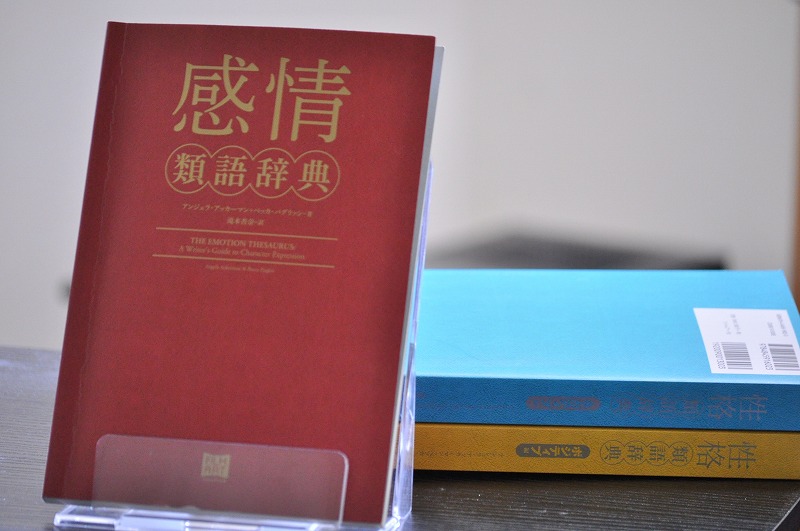
辞書ではなくアイデアブックとして
本書は辞書というよりも、創作指南の読み物 兼 アイデアブックに近い。辞書であれば調べた言葉や表現はそのまま小説本文に用いることができる。
しかし本書の表現はそのままでは使えない。加工を必要とする、材料の形で提示される。
例えば本書で【苦悩】の項目を引いてみよう。
外的シグナルとして
- 食べ物、飲み物が喉を通らない
- 見た目にもわかるほど汗をかく
- 目のまわりが腫れる、苦々しい顔つき
といった感情表現が34個ほど列挙されている。(p.88)
キャラクターの苦悩を表現するのに『食べ物、飲み物が喉を通らない』状態を採用するとして、それを具体的にどのように描写するかは、書き手自身の実力に委ねられる。
本書はヒントを与えてくれるに過ぎない。それを活かすためには(その時点で)ある程度の知識と技術が要求される。
正直に申し上げて、私もあまり本書を活用できてはいない。精進したい……。
冒頭の「感情の書き方」コラムは必見!
冒頭28ページまで「感情の書き方―よくある失敗につまずかないために」という創作コラムが載っており、この内容がとても良かった。
キャラクターの感情描写の《悪い例》と《良い例》が交互に紹介され、なるほどそういう点に気をつけて感情を描くべきだったのか!と目から鱗が落ちる。
じつはKindle版の「無料サンプル送信」で、このコラム全文を試し読みすることができる。
Kindle端末を持ってない人でも、PCアプリ、スマホアプリ経由でKindle本を読めるため、冒頭コラムだけでもぜひ読まれたし。本書で最も価値のあるのが、冒頭の解説部分であるといっても過言ではない。
※上記Amazonページの『無料サンプルを送信』ボタンクリックでサンプル版が配信される。
小説書きにとってはあるあるネタだが、原稿を書いていると必ずと言って良いほどに陥るのが「キャラクターが溜め息を吐きすぎる問題」「キャラクターが微笑み過ぎる問題」だ。
溜め息をついた、微笑んだ、満面の笑みをこぼした……etc 便利な表現ではあるものの、ついつい使いすぎてしまう。本書の著者は、型にはまった感情表現をやめよう!と語る。
もっとよく人間を観察し、感情を掘り下げ、キャラクターの揺れ動く心のようすをリアリティをもって読者に伝えなければいけない。
著者は感情描写を
- 外的なシグナル(ボディランゲージなどの動作)
- 内的な感覚(本能的、生理的な反応)
- 精神的な反応(思考)
の3要素に分類する。この分類法は役に立つし、きっと本書を読む過程で自然と身につくだろう。
私も感情描写は大の苦手なので、良き表現ができるよう努力したい。
本書の不満点など
本書の不満点としては、感情の見出し語が「五十音順」で並べられているのがやや残念だった。
前述のとおり、本書中で紹介される「感情」は75種類しかない。なので感情表現を探そうとするときに、そもそも五十音順で調べる必要性がない。
感情項目を「喜怒哀楽」で並べるだとか、もっとざっくりと「ポジティブ/ネガティブ」で分けて掲載してくれた方が、個人的には親切であるように思う。
万人にはおすすめできないが、発想が面白い本
私が「小説書きならぜひ買ってみて!」と万人におすすめできるのは『てにをは辞典 ※レビュー記事』くらいで、この『感情類語辞典』については相当に人を選ぶかなと感じる。本書を使いこなせる人自体が、おそらく限られている。
ぶっちゃけ私も使いこなせていない。
購入については、Amazonの無料サンプルを見てから判断されるのが無難かもしれない。
感情描写のマンネリから脱出したい人にとって、本書が良きアイデアブックになれれば良いなと思う。