もっとも地味なレトリックであり、知名度も低いシネクドキ(synecdoche―提喩)
修辞技法として意識されることが少ない分、小説描写ではほとんど無意識的に使われるケースが多いです。
しかし、シネクドキという概念を知っていれば、描写を解剖する際に役立ちます。
マニアックであり実用的とも云い難いですが、顕微鏡を覗くようなつもりでシネクドキについて見ていきましょう。
シネクドキのざっくりとした説明は次の図のとおり。
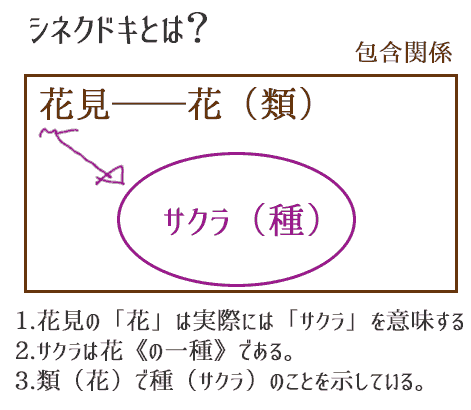
「花見」で桜を表し、「親子丼」で鶏の親子を表し、「酒」で日本酒を表し――などなど、上位概念(類)の言葉を用いて実際には下位概念(種)を表すのがシネクドキの特徴です。(逆のパターンもありますがここでは省略)
重複表現を回避するための役割
早速ですが例文を見てみましょう。便宜的にシネクドキの部分を太文字で表しています。(以下同)
その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルク空港に着陸しようとしているところだった。
(引用:村上春樹『ノルウェイの森』講談社文庫 上巻 p.7)
主人公の乗っている飛行機が、具体的には「ボーイング747」であることが直前の描写では書かれています。しかし同じページ内に「ボーイング747」と連呼するのでは文章がしつこくなるので、引用箇所では「飛行機」と、ボーイング747を包含する概念で言い換えています。
図解すると次の通り。
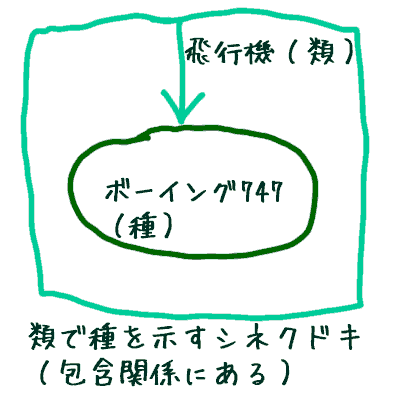
シネクドキのあまりにも地味で目立たない性格に、がっかりされたかもしれません。
ですが小説を書く際には、シネクドキによって重複表現を回避することが結構重要になってきます。
例えば「中肉中背のぱっと冴えないサラリーマン」が次の段落では「男」とだけ表現されていたり。あるいは「アラサーの私より先に結婚を決めた妹に対する、意地悪な嫉妬心」が次の描写では「どす黒い感情」と言い換えられたり。
これらも、具体的なもの(サラリーマン/嫉妬心)をより上位的な概念(男/感情)を用いて示すことで、重複表現を避けています。
小説描写でもっともよく見られるのが、このタイプのシネクドキです。
文章の印象を変えるための役割
もう少しレトリックらしい例を見てみましょう。
でも彼女の病気について正しい知識を得たい人間は一人もいなかった。
(引用:綿矢りさ『ひらいて』新潮文庫 p.39)
登場人物の女子高生が、持病である糖尿病をカミングアウトした際の描写です。教室で、お弁当の時間に明るく振る舞って自分のお腹ににインスリン注射を打つ彼女に対して、周りのクラスメイトたちは冷ややかな視線を投げかけます。
「お菓子の食べ過ぎで発症したんじゃないの?」「病気を見せつけてるんじゃないの?」のような無理解な偏見で、彼女の病気を解釈しようとします。
したがって引用箇所の「人間」とは、実際には「クラスメイト」のことを指しています。
図解すると次の通り。
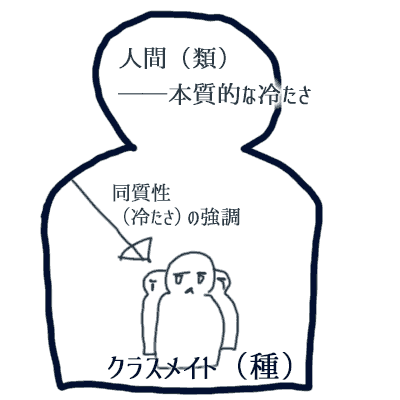
これは先程の重複表現回避とは少し異なる作用をもたらします。
すなわち「彼女の病気について正しい知識を得たいクラスメイトは一人もいなかった」と描写する方がより正確であり、これでも差し支えないのです。
しかしあえて「クラスメイト」あるいは「同級生」という言葉を、上位概念である「人間」という言葉で置き換えている。
このシネクドキの齎す効果は《冷たさと人間の本質》です。
持病を告白した人に冷たい視線が浴びせられるのは、彼女のいたクラスが特殊だったからではありません。
自分や周りと異なる者を異質であると見做す、人間のある醜い性質がそうさせるのです。
ここで「クラスメイト」と言ってしまえば読者にとっては他人事になりますが、シネクドキを用いて「人間(→実際にはクラスメイト)」と表したならば(ああ確かに、人間って残酷なところあるよな……)と感じさせることもできるでしょう。
意味内容は一切変えることなく、しかし文章の印象だけは意図した方向へ変える。
これも地味ではありますが、シネクドキの持つひとつの妙味です。
シネクドキを用いた皮肉法
もっと派手な効果はないんかいとツッコミが入りそうなので、個人的にすごく分かりやすかった描写を挙げてみます。
この記事を書くそもそもの動機となったのが、先日読んだライトノベルでこの表現を見かけたからでした。
あまりにも強烈なヴィジュアルをした物体が、俺を待ち構えていた。
(引用:高野小鹿『彼女たちのメシがマズい100の理由』角川スニーカー文庫 p.11)
タイトルから察していただけるかと思いますが、引用箇所は主人公の幼馴染の彼女が腕によりをかけてつくった「料理」を指しての描写です。
この描写では「料理」を「物体」と言い換えているのです。なんてひどい!
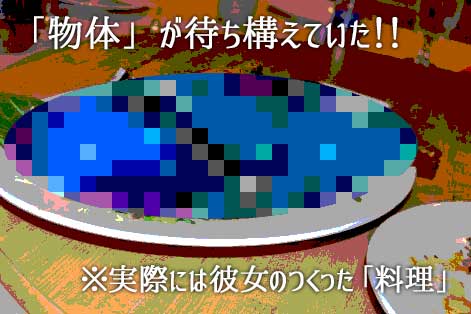
概念的に言えば、「物体」と書いて「料理」を示すのは、メトニミーでもメタファーでもなく、シネクドキです。料理は物体《の一種》ですので。
これの効果はレトリックとしてはけっこう強く、皮肉法や誇張法も入っています。
※ついでに言えば「物体が俺を待ち構えていた」は擬人法の一種。
つまり、実際には描写は料理を指しているのですが《これは少なくとも物体ではあるが、もはや料理には見えない(ほどマズそう……)!》と主張する皮肉と誇張とを内包しているのです。
重複を避けたり印象を少し変えたりと、シネクドキはけっこう防御的かつ静かで大人しい性質を持っているのですが、皮肉が入ると一転して攻撃的になります。
なかなか面白いやつです。
相手を侮辱するシネクドキ
最後に、もっとも高威力であり、物語そのものに影響を与えてしまったシネクドキの例を挙げてみましょう。
小説ではないですが、ディズニー映画の『わんわん物語』(原題:Lady and the Tramp)ではシネクドキが重要な役割を果たします。
えーと、わんわん物語は日本では1956年に公開されました。懐かしい……みなさんご存知……ですよね?
わんわん物語、主人公はレディという血統書付きの女の子の犬です。レディは飼い主の夫婦のあいだで「レディちゃん、レディちゃん」と呼ばれ、愛されて育ちます。
ところが月日が経ち飼い主夫婦の間に赤ちゃんが生まれると、夫婦はレディを邪険に扱うようになります。
「レディちゃん」と呼んでいた夫婦が、あるとき「犬の散歩はどうする?」と会話しているのを聞いて、レディは自分が「犬」と呼ばれたことにショックを受けて家を飛び出してしまいます。(記憶がうろ覚えで、展開は少し違うかもしれませんが、すみません)
このように、名のある血統書付きのレディを「犬」呼ばわりすることは、それが客観的な事実だとしても侮辱的な意味を持ちます。
例えば、正社員が雇われの派遣社員のことを「派遣さん」と呼んだり、あるいは「バイト君」と本人に呼びかけるのを想像してみましょう。その人が派遣あるいはバイトであるというのは事実ですが、名前でなく役職で呼ぶのは失礼に当たります。
(逆に「部長」「課長」「社長」など、目上の役職を呼ぶのは悪い印象を受けない)
《名前―役職》の関係をシネクドキと見るかメトニミーと見るか、ちょっと際どいところですが、個人的にはこれは包含関係を持つのでシネクドキ的であると考えます。
「最近の若者は~」「最近のライトノベルは~」と具体的事象を拡大解釈して、上位概念で語る(いわゆる「主語が大きい」問題)もシネクドキ的な認識によって生じるもので、このシネクドキの侮辱的な性質は少し頭の片隅に入れておいても良いかもしれません。
余談ですが、わんわん物語の本場アメリカでの原題は『Lady and the Tramp』レディとトランプ(ヒロインとヒーローの犬の名前)です。
これを「わんわん物語」と邦訳したのは、ストーリーの趣旨を考えると皮肉的シネクドキだな……とも解釈可能です。もちろん親しみを感じさせるネーミングである点では名訳だと思います。
まとめると、このタイプのシネクドキは、相手を見下すような台詞中で用いると効果を発揮します。
異星から訪れたヒロインが「この地球人が!」と言ったり、宇宙人が「人間の気持ちは分からん」と言ったりするような感じですね。
総まとめ
小説描写に見られるシネクドキには、次のような役割があります。
- 重複表現の回避
- 描写の印象操作
- 皮肉法・誇張法
- 侮辱的な呼び方
シネクドキについては、以前の記事でも別の視点から考察を行いました。

長くなりましたが読んでくださってありがとうございました。
(おわり)